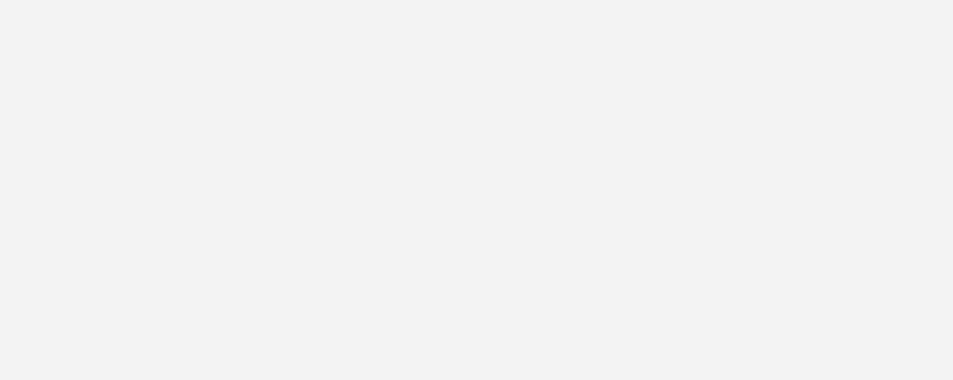{鍵となる文句ひ}
「あふ」より「なふ」へ
【{かぎ と なる あや さかひ}
「あふ」より「なふ」へ】
—
{キーフレーズ}
「あふ」から「なふ」へ
【{キーフレーズ}
「あふ」から「なふ」へ】
[ad#a-auto-1]
[ad#a-336-1]
●「なふ」に當つる漢字‥‥
平ふ。
均ふ。
正ふ。直ふ。
竝ふ。
比ふ。
【●「なふ」に あつる からかた‥‥
なふ。
なふ。
なふ。なふ。
なふ。
なふ。】
—
●「なふ」に当てる漢字‥‥
平ふ。
均ふ。
正ふ。直ふ。
並ふ。
比ふ。
【●「なふ」に あてる カンジ‥‥
なふ。
なふ。
なふ。なふ。
なふ。
なふ。】
[ad#a-auto-1]
[ad#a-336-1]
●「なふ」の意‥‥
平す。
均す。
正す。直す。
竝ぶ。
比ぶ。
【●「なふ」の こころ‥‥
ならす。
ならす。
なほす。なほす。
ならぶ。
くらぶ。】
—
●「なふ」の意味‥‥
平らにする。
平均化する。
(「正しくする」の意の)直す。
並べる。
比べる。
【●「なふ」の イミ‥‥
たいらに する。
ヘイキンカする。
(「ただしく する」の イ の )なおす。
ならべる。
くらべる。】
●「なふ」の語源‥‥
合ふ。
合はす。
【●「なふ」の こともと‥‥
あふ。
あはす。】
—
●「なふ」の語源‥‥
合う。
合わせる。
【●「なふ」の ゴゲン‥‥
あう。
あわせる。】
●「あふ」より「なふ」へ‥‥
「合はす」行ひに別の行ひを加ふる故、
「ahu」に「n」音を加へて「nahu」となりぬ。
【●「あふ」より「なふ」へ‥‥
「あはす」おこなひ に ほか の おこなひ を くはふる ゆゑ、
「ahu」に「n」おと を くはへ て「nahu」と なり ぬ。】
—
●「あふ」から「なふ」へ‥‥
「合わせる」行為に別の行為を加えるため、
「ahu」に「n」音を加えて「nahu」となった。
【●「あふ」から「なふ」へ‥‥
「あわせる」コウイ に ベツ の コウイ を くわえる ため、
「ahu」に「n」オン を くわえ て「nahu」と なっ た。】
[ad#a-auto-1]
[ad#a-336-1]
●「なふ」(語源 → 意転び)一‥‥
(語源)「合はす」
→(低き地に土砂を合はせ、地を平らかにす)
→「平す,平らぐ」
→「均す」
【●「なふ」(こともと → こころ まろび)ひ‥‥
(こと もと)「あはす」
→(ひくき つち に つちすな を あはせ、つち を たひらかに す)
→「ならす,たひらぐ」
→「ならす」】
—
●「なふ」(語源 → 転意)1‥‥
(語源)「合わせる」
→(低い地盤に土砂を合わせて、地面を平坦にする)
→「平す,平らにする」
→「均す,平均化する」
【●「なふ」(ゴゲン → テンイ)イチ‥‥
→(ひくい ジバン に ドシャ を あわせ て、ジメン を ヘイタン に する)
→「ならす,たいらに する」
→「ならす,ヘイキンカする」】
●「なふ」(語源 → 意転び)二‥‥
(語源)「合はす」
→(低き地に土砂を合はせ、地を平らかにす。)
→「平す,平らぐ」
→(平らかなる地面といふ、然るべき基準に、盛れる土を合はす。)
→(然るべき基準に、或る物を合はす。)
→「直ふ,正ふ」
→(基準と爲る物と或る物を竝べて比ぶ。)
→「竝ぶ」「比ぶ」
【●「なふ」(こともと → こころ まろび)ふ‥‥
(こと もと)「あはす」
→(ひくき つち に つちすな を あはせ、つち を たひらかに す。)
→「ならす,たひらぐ」
→(たひらかなる つちおも と いふ、しかる べき もと のり に、もれ る つち を あはす。)
→(しかる べき もとのり に、ある もの を あはす。)
→「なふ,なふ」
→(もと のり と なる もの と ある もの を ならべ て くらぶ。)
→「ならぶ」「くらぶ」】
—
●「なふ」(語源 → 転意)2‥‥
(語源)「合わせる」
→(低い地盤に土砂を合わせて、地面を平坦にする。)
→「平す,平らにする」
→(平坦な地面という、そうあるのが相応しい基準に、盛った土を合わせる。)
→(そうあるのが相応しい基準に、ある物を一致させる。)
→(「正しくする」の意の)「直す」
→(基準となる物とある物を並べて比べる。)
→「並べる」「比べる」
—
【●「なふ」(ゴゲン → テンイ)ニ‥‥
(ゴゲン)「あわせる」
→(ひくい ジバン に ドシャ を あわせ て、ジメン を ヘイタン に する。)
→「ならす,たいらに する」
→(ヘイタンな ジメン と いう、そう ある の が ふさわしい キジュン に、もっ た つち を あわせる。)
→(そう ある の が ふさわしい キジュン に、ある もの を イッチさ せる。)
→(「ただしく する」の イ の)「なおす」
→(キジュン と なる もの と ある もの を ならべ て くらべる。)
→「ならべる」「くらべる」】
≪助け物等【たすけ もの など】(参考文献等)≫
・大野晋 (1988)『日本語の文法〈古典編〉』角川書店
・金田一春彦 (1977)『新明解古語辞典』三省堂
・藤堂明保 (1978)『学研漢和大字典』学研プラス
・やまとことばのみちのく
(アクセス日:2018/6/15)
↓応援クリック、いつもありがとうございます。