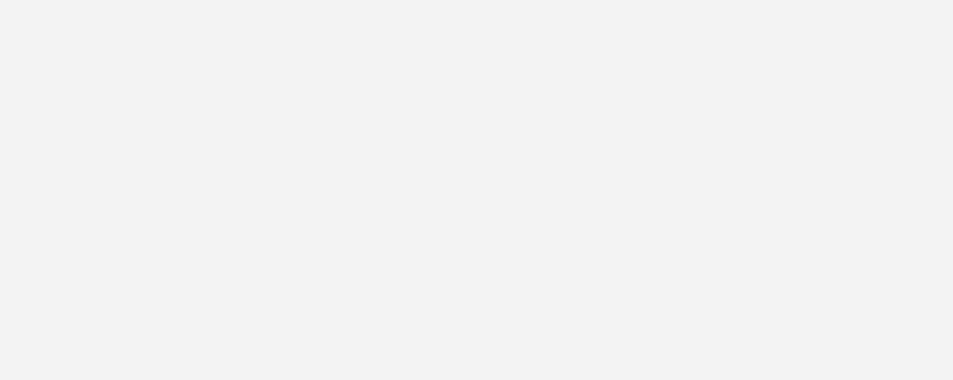●1日~9日
1 ひ
1日 ひ か → ひ と ひ
2 ふ
2日 ふ か → ふ つ か
3 み
3日 み か
4 よ
4日 よ か → よ つ か
5 い
5日 い か → い つ か
6 む
6日 む か → む ゆ か
7 な
7日 な か → な ぬ か
8 や
8日 や か → や う か
9 こ
9日 こ か → ここ ぬ か,ここ の か
●10日~90日
10 と
10日 と か,と を か
20 ふ そ,は た
20日 ふ そ か,は た か → は つ か
30 み そ
30日 み そ か
40 よ そ
40日 よ そ か
50 い そ
50日 い そ か
60 む そ
60日 む そ か
70 な そ → なな そ
70日 な そ か → なな そ か
80 や そ
80日 や そ か
90 こ そ → ここの そ
90日 こ そ か → ここの そ か
(「そ」は十の意.)
[ad#a-auto-1]
[ad#a-336-1]
●100日~900日
100 もも
100日 もも か
200 ふ もも → ふた もも
200日 ふ もも か → ふた もも か
300 み もも
300日 み ももか
400 よ もも,
よ ほ(よお)
400日 よ ももか,
よ ほ か(よおか)
500 い もも,
い ほ(いお),いつ ほ(いつお)
500日 い もも か,
い ほ か(いおか),いつ ほ か(いつおか)
600 む もも,
む ほ(むお)
600日 む もも か,
む ほ か(むおか)
700 な もも,
な ほ(なお),なな ほ(ななお)
700日 な もも か,
な ほ か(なおか),なな ほ か(ななおか)
800 や もも,
や ほ(やお)
800日 や もも か,
や ほ か(やおか)
900 こ もも,
ここの ほ(ここのお)
900日 こ もも か,
ここの ほ か(ここのおか)
(「もも」,「ほ」は百の意.)
[ad#a-auto-1]
[ad#a-336-1]
●11日,12日など…
11 と あまり ひ
11日 と か あまり ひ か,と を か あまり ひ と ひ
12 と あまり ふ → とを あまり ふ
12日 と か あまり ふ か → と を か あまり ふ つ か
21 ふそ あまり ひ,はた あまり ひ
21日 ふそ か あまり ひ か,はつ か あまり ひ と ひ
22 ふそ あまり ふ,はた あまり ふ
22日 ふそ か あまり ふ か,
はた か あまり ふ か → はつ か あまり ふ つ か
23 ふそ あまり み,はた あまり み
23日 ふそ か あまり み か,
はた か あまり み か → はつ か あまり み か
24 ふそ あまり よ,はた あまり よ
24日 ふそ か あまり よ か,
はた か あまり よ か → はつ か あまり よ つ か
25 ふそ あまり い,はた あまり い
25日 ふそ か あまり い か,
はた か あまり い か → はつ か あまり い つ か
●5、6日…
五六日 いかむか → いつかむゆか
●変遷例…
「八日」の読み:「やか」→「やうか」→「ようか」
●漢数字…
21日 廿一日
22日 廿二日
23日 廿三日
[ad#a-auto-1]
[ad#a-336-1]
≪参考文献等≫
・中村幸弘 (2007)『ベネッセ全訳古語辞典』ベネッセコーポレーション
・源氏物語イラスト訳で古文の偏差値20upする勉強法
https://ameblo.jp/aiaia18/entry-12195583167.html
(アクセス日:2017/9/7)
↓応援クリック、いつもありがとうございます。