その
・
・
・
・
・
≪參ね物(參考文獻)【たづね もの(サンコウ ブンケン)】≫
・林達夫ほか (1972)『世界大百科事典』平凡社
・金田一春彦 (1977)『新明解古語辞典』三省堂
・藤堂明保 (1978)『学研漢和大字典』学研プラス

その
・
・
・
・
・
≪參ね物(參考文獻)【たづね もの(サンコウ ブンケン)】≫
・林達夫ほか (1972)『世界大百科事典』平凡社
・金田一春彦 (1977)『新明解古語辞典』三省堂
・藤堂明保 (1978)『学研漢和大字典』学研プラス
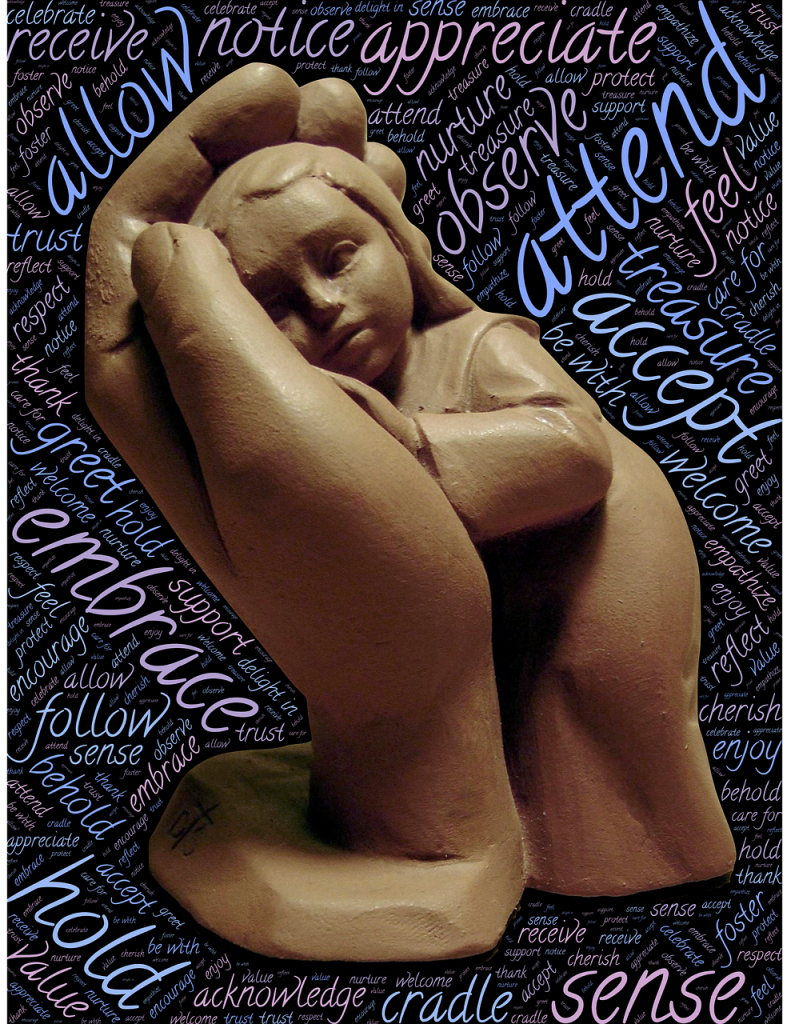
「わ ゐ う ゑ を」(wa wi wu we wo) の「ゐ」。
「ゐ」の
・
・
・
(「
「
「
(
[訳] 「
「
「
「ゐ」の
「ゐ」の
≪參ね物(參考文獻)【たづね もの(サンコウ ブンケン)】≫
・林達夫ほか (1972)『世界大百科事典』平凡社
・金田一春彦 (1977)『新明解古語辞典』三省堂
・藤堂明保 (1978)『学研漢和大字典』学研プラス

菊理媛神(くくりひめのかみ)
白山比咩神(しらやまひめのかみ)
撞賢木厳之御魂天疎向津媛命(つきさかき いつのみたま
あまさかる むかつひめのみこと)
湍津姫神・滝津姫神(たぎつひめのかみ)
乙橘姫命・弟橘媛命・音橘姫命(おとたちばなひめのみこと)
伊都能売神(いづのめのかみ)
早池峰の神(はやちねのかみ)
織姫命(おりひめのみこと)
白龍神(はくりゅうしん)
女神イシス(めがみ いしす)
ケルトの女神
≪參ね物(參考文獻)【たづね もの(サンコウ ブンケン)】≫
・林達夫ほか (1972)『世界大百科事典』平凡社
・金田一春彦 (1977)『新明解古語辞典』三省堂
・藤堂明保 (1978)『学研漢和大字典』学研プラス


「や」の
・その
・それ
・
・
「や」の
「や」のつく
「や」の
≪參ね物(參考文獻)【たづね もの(サンコウ ブンケン)】≫
・林達夫ほか (1972)『世界大百科事典』平凡社
・金田一春彦 (1977)『新明解古語辞典』三省堂
・藤堂明保 (1978)『学研漢和大字典』学研プラス